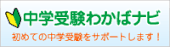アトピー性皮膚炎の患者は全国で約35万人といわれる。近年は、患者数の増加とともに大人になっても悩まされる人も多い。薬を正しく使うとともに、心理的なアプローチも大切だという。
◆分かっていても
アトピー性皮膚炎は皮膚のバリア機能がほころび、侵入する抗原を防ごうとする体の免疫機能によって、炎症やかゆみを引き起こす。かくと皮膚の組織がさらにダメージを受け、炎症が広がってしまう。ただ、「分かっていてもやめられない」「眠っている間にかいてしまう」という人は多い。
東京慈恵会医科大付属第三病院皮膚科診療部長の上出(かみで)良一教授は「患者の中には、かゆくなくても無意識にかいてしまう動作(嗜癖的掻破(しへきてきそうは))がある人が多い。不安だったり、逆にほっとしたりしたときです。かくという行為が、安心、ストレス解消につながってしまう」と話す。
ストレスなどによる嗜癖的掻破がアトピーを悪化させ、治りにくくしている面があるとして、上出教授は外来での初診時、少なくとも15分程度の問診を行っている。家族や学校、職場といった生活環境全般についても聞く。「一番つらいと感じている話題に触れると、無意識にかこうとするしぐさが出る。ストレスをなくすのは無理でも、それに気づくだけで嗜癖的掻破を減らすことができる。アトピーは禁煙同様、『治す』というより『抜け出す』病気だと考えています」
症状がひどく、引きこもりがちだったり、鬱になったりしてしまう人もいるが、「専門的な精神ケアが必要な人はそんなにいない。特に子供は、できなかったことを指摘して『頑張れ』というより、できたことを褒めた方が治療に前向きになる」と上出教授。
◆ステロイドへの誤解
他の皮膚疾患に比べ、情報があふれているのもアトピーの特徴。ステロイド外用薬の使用は、日本皮膚科学会や日本アレルギー学会による診療ガイドラインで中心に位置づけられ、正しく使えば効果は高い。だが、「怖い」という声は強く、インターネットの普及が情報の混乱に拍車をかけている。
ステロイド外用薬は通常、指先から第一関節までの量を大人の手のひら2つ分を目安に塗る。しかし、怖い薬という思い込みから量が少なく、結果として「塗っているのに効かない」という誤解を生む。また、ステロイドで改善しても、自己判断で塗るのをやめたり、量を減らしたりすると、皮膚の奥には炎症が残っているため、再び悪化してしまう。肌がしっとりした手触りになるまでは薬を使い、赤みが消えても乾燥しているうちは保湿剤だけのケアは危険だ。
診察時間が限られ、正しい薬の使い方やケアの仕方を伝えきれない医師も多い。上出教授は17年前から月に1度のペースで、患者やその家族が集まる「アトピーカフェ」(http://atopy.com/)を開いている。同院で診察を受けていなくても参加でき、症状や経験、疑問など語り合い、スキンケアの方法などを学べる。
■病状の診断に血液検査
アトピー性皮膚炎の病状把握では、総合的なアレルギー反応を調べる血清総IgE値▽好酸球(白血球の一種で炎症の程度を把握)▽LDH(炎症で細胞が破壊されると生成される酵素)▽TARC値(炎症を起こしている場所に細胞を呼び集める因子)-をそれぞれ血液検査で調べる。平成20年に保険適用となったTARC値検査はアトピーの重症度を測る指標。糖尿病におけるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値のように、測定時ではなく一定期間の病状が把握できるため、ステロイド外用薬などの処方の目安に利用されている。
(2012.9.12 ヤフーニュースから転載)
 幼稚園情報なら 『関西版 幼稚園受験.com』
幼稚園情報なら 『関西版 幼稚園受験.com』